
英語を「聞き取れる耳」に変えるリスニング戦略
リスニング力が伸びない原因とは?
「聞いてるのに聞こえない」問題の正体
英語の音声を毎日聞いているのに、「なんとなく雰囲気はわかるけど、細かい単語や表現が入ってこない……」という悩みを持つ人は少なくありません。この現象の正体は、「知っているはずの単語が、音として認識できていない」ということ。
特に日本語にはない音のリズムや抑揚、母音と子音の連結(リンキング)が聞き取りを難しくします。聞き慣れない発音や早口の英語では、単語が「消える」ように感じるのです。
音のつながりと脱落に慣れる方法
たとえば “What do you want to do?” は、実際の会話では “Whaddaya wanna do?” のように聞こえます。これは音が連結し、一部が脱落する「リエゾン」や「省略」が起きるためです。
これに慣れるには、実際の音をスクリプトと一緒に確認しながら繰り返し聞くことが大切です。自分で発音してみると、「あ、確かにこうなるのか」と納得できます。音読やシャドーイングと組み合わせると、より効果的です。

リスニング力を底上げする方法
シャドーイング vs ディクテーションの使い分け
- シャドーイングは、聞こえた音声を即座にまねて発声するトレーニング。耳と口を同時に動かすことで、リスニングとスピーキングの回路を同時に鍛えられます。英語のリズムやイントネーションを体感的に覚えるのにも効果的です。
- ディクテーションは、聞いた内容を一語ずつ書き取る練習。細かい音の聞き取り精度を上げたいときに最適です。初級者から中級者に特におすすめ。
どちらも効果的ですが、目的によって使い分けるのがコツです。例えば、「内容がざっくり分かるけど正確に聞き取れていない」と感じたらディクテーション、「全体のスピードやリズムについていけない」と感じたらシャドーイングを取り入れると良いでしょう。
倍速再生で脳を鍛える練習法
意外と効果的なのが倍速再生(1.25倍〜1.5倍)でのリスニング練習。普段より少し速いスピードで聞くことで、脳の処理速度が鍛えられ、通常のスピードが「ゆっくり」に感じられるようになります。
慣れるまではストレスを感じるかもしれませんが、1日5分からスタートし、徐々にスピードを上げていくと、自然と耳が鍛えられていきます。

神戸市外国語大学でできるリスニング強化習慣
ネイティブ教員の授業を「音源化」する
神戸市外国語大学では、ネイティブの教員による授業を受ける機会が多くあります。この貴重な機会を「聞いて終わり」にするのではなく、自分用に“音源化”して復習に使うのがおすすめです。
たとえば、授業中の発言ややりとりをメモし、家で再現したり、先生にお願いして話した内容の再確認をしたり。「あの表現、あの言い回し、もう一度聞いて覚えたい」と思った部分を音読やシャドーイングに活用すれば、授業がそのままリスニング教材になります。
スクリプト付きコンテンツの使い倒し方
授業で扱ったリーディング教材やスピーチスクリプトは、リスニングトレーニングにも流用可能です。特に、大学の教材は語彙や文構造がしっかりしているため、「聞き取れる+意味が理解できる」力を同時に鍛えることができます。
さらに、YouTubeやPodcastなどのスクリプト付き素材も積極的に活用しましょう。再生速度を調整したり、聞き取れなかった部分をスクリプトで確認することで、学習効率がぐんとアップします。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
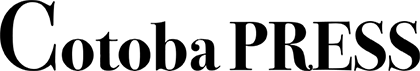
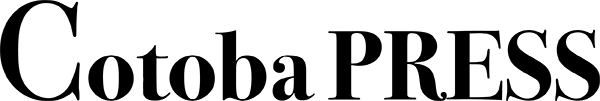


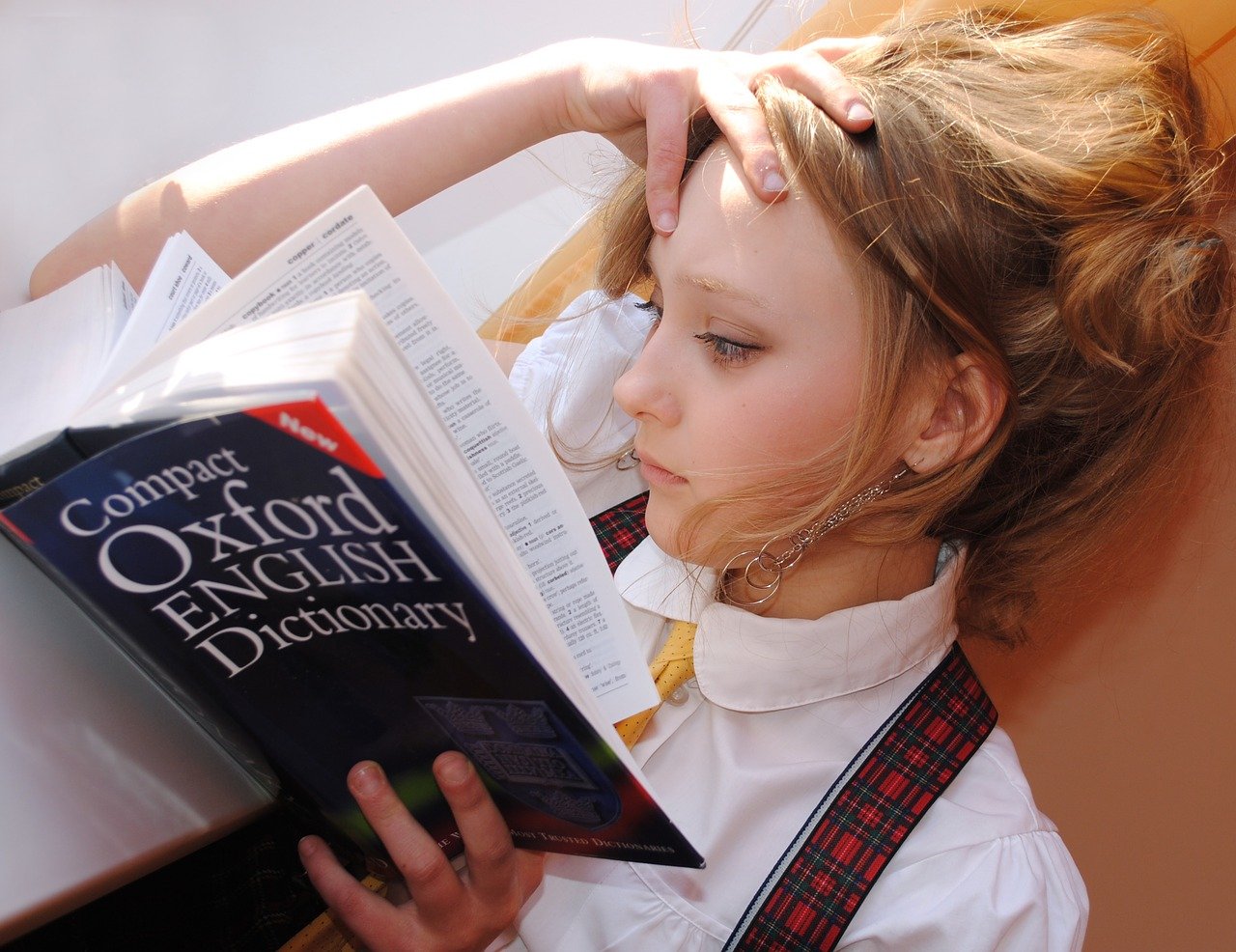

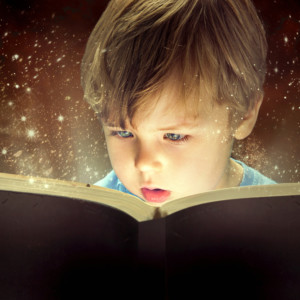



この記事へのコメントはありません。